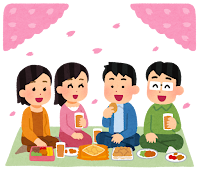曇り空の京都東山です。昼間は暑く感じるようになってきました。いよいよ桜の開花が気になってきましたが、雙林寺界隈の桜はまだつぼみの状態です。
ということで、お花見について調べてみました。お花見は、その言葉通り、桜の花を鑑賞しながら宴を楽しむことですね。
歴史は奈良時代に遡り、当初は梅の花を鑑賞する行事として始まったそうです。平安時代になり、桜が主となり、812年に嵯峨天皇が神泉苑で催した「花宴の節」が桜を鑑賞するお花見の起源とされているようです。その後、安土桃山時代に豊臣秀吉が「醍醐の花見」など、大規模な花見が開催されるようになり、庶民にも広がっていったそうです。
雙林寺も桜の名所で知られ、1584年、豊臣秀吉が花見の宴を催し、前田玄以に命じて、花樹保護の制札を立てさせたという由緒があります。
江戸時代なると徳川吉宗が桜の植樹を奨励し、隅田川堤や飛鳥山などがお花見の名所として知られるようになり、庶民らは、お弁当やお酒を持ち寄って、桜の下で宴会を開くようになり、これが現代のお花見の形へとつながっていったとのことです。
桜の儚さや美しさが日本人の心に響き、現在でもお花見は春の風物詩として親しまれています。京都の桜はあちこちで見られますが、どこの桜がおすきでしょうか。今日も楽しい一日を。